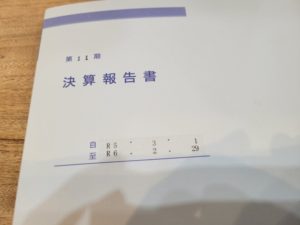和歌山や南大阪で地産地消の家、
大工さんの手刻みで建てる木の家、
設備に頼らない、建築でできることを
考えて、信念をもって家づくりを
おこなっている、和秋建設の前田です。

今回の令和6年能登半島地震が起きたことで
地震保険について考えてみました。
地震保険は地震や噴火、津波のほか、
これらが原因の火災で建物や家財が損害を被った場合、
条件に応じて一定の保険金が支払われます。
単体では加入できず、任意で火災保険とセットで加入する。
保険料はその分上乗せして支払う仕組みになっています。
地震保険は被害の全額を補償するわけでもない。
建物や家財の損害状況に応じて全損▽大半損▽小半損▽一部損――の4段階に認定した上で、
支払いの限度額は最大で、付帯元の火災保険で支払われる保険金の50%までに抑えられています。
地震が原因で火災が起こって燃えてしまった場合
火災保険はおりません、地震保険に入っておかないと
保険金は出ません
また家財も火災保険の家財ではなく地震保険の家財に入っておかないと
いけません
火災保険(家)火災保険(家財)地震保険(家)地震保険(家財)
この4種類に入ってフル加入になります。
お金はかかりますが
今回の令和6年能登半島地震が起きた石川県
地震保険の加入率は地域によってばらつきがあり
被害の大きかった石川県の加入率は64.7%と全国平均を下回っているそうです。
地震保険料を決める際の参考となる政府の地震調査委員会が示すデータでは、
日本海側より太平洋側の地震の発生確率が高く出ていたみたいです。
20年に作成された最新のデータでは、
今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率は、
東京都が47.2%だった。これに対し、石川は6,6%、富山も5.2%と低かった。
低い分地震保険料も安いのですが
この確率だけ見ると大丈夫かなと思ってしまうのも仕方ないのかなと思います。
確率だけで見ると高い低いはあると思いますが
地震大国の我が日本どこに住んでいても
起こる時は起きると考えた方がいいと思います。
保険はお守りと考え
入れるように出来るだけ段取りして
家の方は建築で出来る事
地盤の調査をして対策する
耐震等級3を目指す
制震ダンパーなどを設置して
地震の揺れを軽減するなど
命と暮らしを守るため
予算的には 少し上がりますが
建築で出来るこれらのことも
地震が起きたときのお守りになると
考えています。
今までおこなってきた家造り
耐震等級3や制震ダンパーなど標準仕様にしていますが
実際地震が起きてどうなったかは起こっていないので
検証することはできないのですが
かといって起こってほしくもありませんが
私が生きている間には
一回くらい起こるのだろうと
会社にも食料と水の備蓄をしておこうと
考えている前田なのでした。

昭和39年5月29日生まれ
一級建築士
一級施工管理技士
宅地建物取引士
和歌山県和歌山市生まれ
地産地消の考えのもと全国に誇れる資源の紀州材を環境に優しい自然乾燥で大工さんの手刻みにこだわり、家の中の空気がおいしいなと思える家づくりを行っています。